松井周の人間標本室 — 大丸有の人たちの標本転生をレポートした1週間後、仕掛け人の松井周に単独インタビューを行った。

劇作家、演出家、俳優、「サンプル」主宰 松井周
コロナを経て、松井が今考えている新しい演劇のアプローチとはどう言ったものなのか。そこには従来の演劇からの飛躍の可能性を含んだ実験があった。
「標本室」を始めるきっかけは何だったのでしょうか。
そもそも2011年の東日本大震災のすぐ後にサンプルクラブというスタディグループを作り、本について話したり、僕の作品の感想を言い合ったり質問を受けたり、ということをやっていました。劇団としてのサンプルを解散して2017年に僕個人のユニットにした際、サンプルクラブは一旦解散したのですが、コミュニティみたいなことはずっとやりたいと思っていました。
サンプルのワークショップ(WS)はずっと続けていました。講師陣は全員が演劇のプロというわけではなく、さらに一般市民の方々も参加するWSで、その面白さがずっと僕の中にあったからです。実際に新潟に1週間合宿に行ったりもするぐらい、熱心にやっていました。
そこから2020年に「標本室」というプロジェクトをやろうということに決めました。サンプルクラブやWSでやっていた面白さをなんとか継続させたい、それもプロアマ関係なく、年齢も地域も関係なく、なるべく集まって何かをしようという企画でした。そのプロジェクトを始めようとしたらいきなりコロナになってしまったんです。集まることに意味があると思って始めたのですが集まれなくなってしまったので、Slackを介してのチャットや部屋を作り、発表するための作品の製作途中経過をそこにあげていくようなことをやりました。
その活動に対してアーツカウンシルから3年間の助成金が出たのです。
その折、YAUが丸の内のビルの部屋を稽古場として使いませんか、という公募をしていたのでそれに応募しました。「標本室」は発表会をしてなんとか3年間続けたのですが、その流れで、YAUから今回の「大丸有標本室」、”大丸有*のワーカーの人たちと作品作りをしませんか”と声をかけていただき始まった、という形です。
*大手町、丸の内、有楽町の略
劇団名のサンプルは「標本室」の標本と同じところから命名されたのですか。
完全にそうです。サンプルは見本、標本というところから来ています。僕は(演劇は)常々偽物っぽいなと思っていましたから。人間ってもとは空っぽな器から出発して、お母さんや家族の真似をしたりしながら成長していきますよね。真似をしてそれを稽古しながら覚えていくもので、そもそも何かを持って生まれてきたわけではなく、あとから人の様をなぞっているだけなので、僕には人は人間の真似をしているとしか思えないんです。そこからサンプルという劇団名が浮かびました。
人は皆、日常で演技をしながら生きていて、それぞれに役割みたいなものを背負っている。例えば父親、母親、後期高齢者など、分類されやすいカテゴリーでの役割を多くの人が甘んじて受け入れているということです。一方で、その人でしかないこだわりやクセを持っている。その二つが合体したものが僕の中での“標本”というイメージです。なので、人間は分類されやすい何かを身にまとっているのだけれど、その一方でその人らしさを持っている。その両方を使って面白がる何かをやりたいと思って「標本室」をやっています。自分の中にあるその2つの面をうまく使い分けながら、ゲームのように会議をし(なりかわり標本会議)、また丸の内で働きながら自分だけが持っている何かこだわりのようなものを出して作品を作る(標本転生)といったことをしています。
「標本室」の活動がコロナと時期が重なったということですが、コロナ禍で考えたことはどのようなことでしたか。
演劇的に言うと、作り手が作ったものを観客が客席で観るというやり方は本当に奇跡的なことだったということを痛感しました。その方法ではコロナで誰かが欠けたら成立しません。なので、そうではないやり方を見つけなければ、と思いました。たとえコロナが去ったとしても、また何かが起きて、外出禁止とかになったら客席で観られない状況になると思うので、演劇の今までのやり方とは違うやり方というのを考えるようになったきっかけではありますね。
2021年に予定していたさいたまゴールド・シアター*の「聖地2030」はコロナで中止になりました。そこで考えたのが、誰かが出演できなくなったとしても他の人が代わりに出られるようにするために、即興的なものを取り入れた方が良いのではないかということです。それだと、毎回違うものになるのですが、うまく枠組みを作れば、誰かが体調が悪くなったとしても大丈夫。高齢者の方々も安心して参加出来る仕組みを作ろうと思ったのです。そうして作っていったのが先日上演した、やはり高齢者が出演する「終点 ―まさゆめ」という作品で、そこでは役者さんたちが各々自分の台詞を創作しています。
*さいたまゴールド・シアター:2006年に故蜷川幸雄の指揮の元で創設された55歳以上の劇団員からなる高齢者劇団
コロナ禍では感染者が出ると公演中止で作品がまぼろしになってしまうこともあって、それはとんでもないことだ、と思ったのです。
やはりその頃から、やり方を変えていくことを考えるようになりました。巷ではオンライン演劇などの試みもありましたが、僕としてはそれは難しいだろう、と。やはり集まって感じるものとオンラインでやれるものというのは根本的に情報量が全く違うので、集まりながらも安全にやる方法を考える中で即興劇みたいなものを考えるようになりました。
「標本室」の参加者をプロアマ問わず誰でも、としているのはなぜですか。
俳優を専門としている方々と作品を作るのもとても楽しいのですが、その人らしさみたいなものはプロアマ関係なく、誰でも何かしら持っています。もちろんプロの人たちの方がその人らしさを出しつつあらゆる役になりきったり出来るのですが、その人らしさを引き出すのに少し時間がかかるとは言え、プロでない人たちと一緒にその引き出す作業をして楽しみたいというのがあります。それは純粋に僕の好奇心ですかね。
実際、参加者たちはどう感じていると思われますか。
ユーチューバーとかTikTokに投稿している人とか、表現することを専門(プロで)にやっているわけではないけれど自分の日常を見せたり、絵を描いたり、歌ったりしたいというのは誰もが持っている欲求だと思っています。それに関しては専門家としてのクオリティーがどうだと言うよりも、観ている側はむしろ“自分と似たような人がいる”とか“自分とは違うけれどこの人面白い”とかいうことを基準に観ているのだと思います。そのように生活の中で発信していくことがどんどん当たり前になってきていて、僕はその当たり前になっていることに励まされています。今までは“このクオリティーに達していないものはダメ”みたいに切り捨てられていたと思うのですが、そもそもそれを決める基準って何、と思うわけです。
演劇に関して言えば、俳優や演出家は何かの試験に受かったわけでもなく、やりたくてやっているだけなのですから、そこに評価を加えることはやりたくありません。
もちろん誰もが驚嘆する最先端の舞台や演劇というものは存在するのですが、生きている中でちょっと踊ってみたり、生活の一端を見せたりするのも人の営みの一つの表現であり、それはそれで面白いと思っています。

標本転生ワークショップの参加者
「なりかわり標本会議」*では必ず最後に発表会を設けていました。
*なりかわり標本会議:参加者はカードを引き、そこに書かれた役割に“なりかわって”テーマについて話し合う企画
最近その発表の仕方として考えているのが、ただ観てもらうというよりも客席でも同時に舞台上で起こっていることに参加してもらえないかということです。そこで、「なりかわり標本会議」の発表会で、舞台上にいる人たちはカードを引いてそこに書かれた役割に成るのですが、観客にも会場に入ってくる時にカードを引いてもらい、何らかの設定になってもらっています。標本会議では途中で自分の過去、例えば 「不倫」 や 「パワハラ」 をしていたなどの行いが明かされる仕組みになっているのですが、舞台上の人たち同様にお客さんにもカード、例えば「万引き」と書かれたカードを引いてもらっています。さらに、休憩時間中に舞台の誰を支持するのかを表明するシールを身体に貼ってもらうようにしています。
そのように舞台上と客席の間でインタラクティブにこの舞台を作っていくことを自覚してもらうような仕組みを作っています。
演劇は観るよりもやる方が面白いと思っていて、観ることに特化してきた演劇をみんなでやる方向にしていくのが良いと感じています。
その際に 「ここはゲームの場です」という設定があり、本人がダイレクトにそのまま発言するというのではなく、フィクションに包まれて参加するというのが大事だと思っています。例えば演劇舞台の“客いじり”はとても暴力的だなと思っているのですが、と言うのも、舞台上の人たちはフィクションの中にいるのでその役として客席に降りて行って観客をいじるのですが、観客はフィクションをまとっていないのでダイレクトに晒されるからです。これまでの作り手側のある種舞台の上の立場の方が優先されるみたいな感じにはしたくないというのがあります。
継続中の大丸有の人たちとの「標本室」 「標本転生」で大丸有の人たち特有の反応はありますか。
「これ本当に面白いんですかね?」と結構聞かれますね。(笑)
僕はその人が日常でこだわっていることが面白いと思っていて“それすごく面白いです、ぜひ作品にしてください”と言っても、彼らはどう作品にしたら良いのか、何を面白がられているのか、何をしたら良いかがわからないという不安がずっとあったように思います。
おそらく、自分はアーティストではないのでやっていることがチープに思えるという不安を抱いているのではないでしょうか。アートをやるからにはこれくらいのクオリティーのものをやらなくてはいけないと言ったような認識を持っている方も多いのかもしれません。会社の仕事というのは納期までに完全なものを提出しなければいけないというのが基本なので、僕が“完成形はありません。完成させなくて良いです”と言えば言うほど彼らは不安になった部分はあったかもしれません。自分が好きなもの、何となくこだわってきたものを“それ良いですね、それを作品にしませんか”と言ってもどうしたら良いかわからないみたいなことがずっとあったと思います。
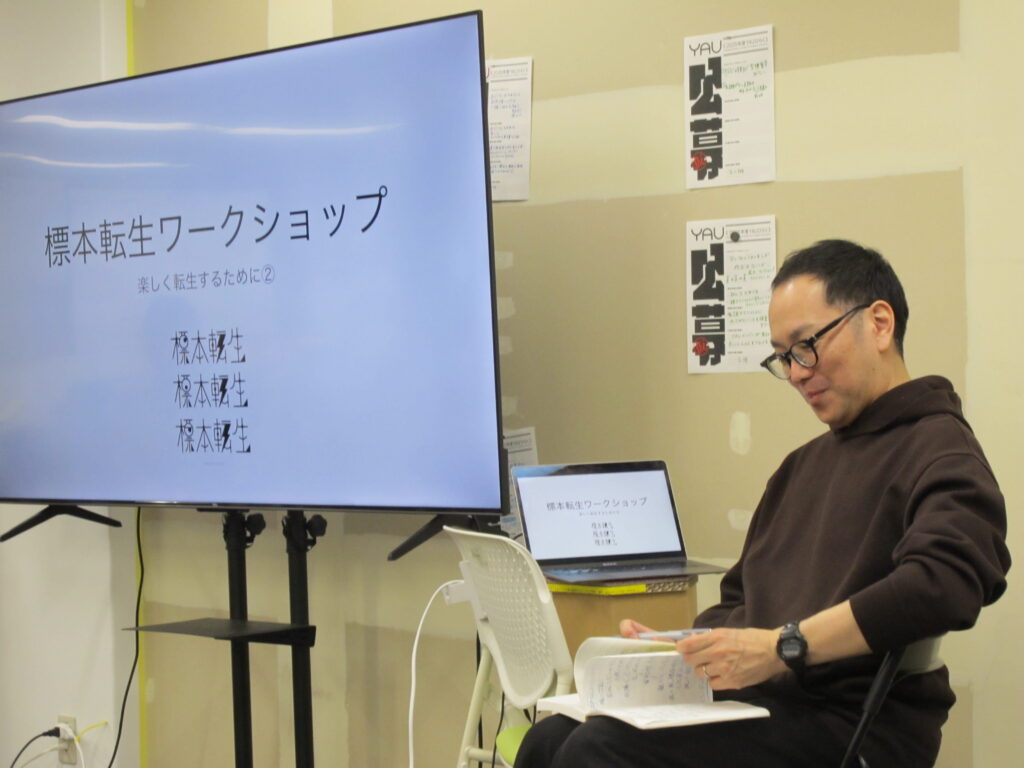
「標本室」で行っていることはどの点で演劇と結びつくのでしょうか。
演劇というよりも、みなさん生きているだけで標本なので、その人なりの何かであれば良いという言い方をしています。その人の欲望と作業がちゃんと一本で繋がっていれば良いのです。
例えば演劇でも、誰かが舞台に登場した時にはその人は何か用があるから出てきているわけで、そこには違和感がない。僕はそうやって俳優を見るように、その人の欲望とやろうとしていることの違和感がなければオッケーだと思っています。
例えばあるメーカーの飲料が好きでたまらない人はその飲料についてどんどん調べて、それを使って作品を作る、というだけの話なんです。それなのに、はじめから一般論や社会性に終始して、そもそも自らの欲望というか動機からズレてしまっていませんか?と声をかけます。往々にして“うまい、利口な答え”を考えすぎてしまうのですが、もっと自由であって良いと思っています。
僕は単純に、自分の欲望に気づいてそれを客観的に外に発表していくということを多くの人に経験してもらいたいと思っているのです。それを一回経験すると、それまでとは違った定まった視点を社会に置くことができて、そこからいろいろなことが見やすくなる。他者からも「あなたはそういう視点を持つんだね」と認識されやすくなるし、一度その基盤を持つと、またやりたいと思うようになると思います。
とは言え、松井さんは演劇人です。今後どのように「標本室」の活動を演劇と結びつけていくのでしょうか。
2023年上演の「イエ系」はオーディションで集まった方たちとの創作で、俳優として活動してきた方がほとんどの中に演劇が初めてという方も混ざっている作品でした。そのような作り方をしたのは、いままでの演劇の定義の中での上手さとか下手さの評価とは関係のないもっと違った面白さ、その人の持つこだわりというものを引き出すことをしたかったからです。「標本室」をやっている中で、それぞれのこだわりを引き出すということに関して、例えばある人が昔楽しく思っていたことや夢中になり始めたことについてちょっと背中を押すだけで、どんどんその人自身が面白い作品を作っていくということがわかってきました。基本的には標本室で取り組んだ“きちんとその人の話を聞く”ということぐらいしかやっていないのですが、それをしっかり舞台作りに取り入れてみました。
「標本室」でのやりとりの経験を戯曲の執筆に活かした部分もあります。「イエ系」には結構役者のアドリブが含まれているんです。“僕が書いた台詞の他に絶対に自分で台詞を足してください”と頼みました。最初はぎこちないのですが、やっていくうちにその人の良さみたいなものが出てきて、自由になっていきました。
「イエ系」の上演でのことです。昼と夜の2回公演があり、従来の演劇の観点からすればブラッシュアップ(より良くする)して洗練された夜公演の方が昼公演よりも良かったということになったのでしょうが、その時僕はそうは思いませんでした。役者たちが余裕を持って演じることで洗練されてしまうとすごく演劇っぽく、従来の演劇の価値観に依っているものになっていると思ったので“もっとみんなブラッシュダウン(ブラッシュアップの反対で磨き上げないこと)してください”と言いました。
役者にブラッシュダウンを要求する松井さんの作りたい演劇とはどのようなものになっていくのでしょうか。
演技の面で言うと、その日その場で起こったことを大事にしてほしい、いつもブラッシュダウンした舞台を作っていきたいと思っています。舞台は日が経つと余裕が生まれるので、新鮮さを装った上手さみたいなものが出来てくるのですが、そうではなく、その時その時に起きていくことにきちんと襲われたり、丁寧に追っていくような芝居の場合はある意味「忘却」という名のブラッシュダウンが必要なのではないかと感じています。解像度を落とすと言うか、荒削りに戻すと言うか。ある意味、無茶ぶりではあるのですが。
戯曲に関してはどうでしょう。
「イエ系」はサンプル、つまり標本化している世の中、擬似家族を扱っているのですが、擬似でも家族になれるとしたら、ある種おぞましい部分がありながら楽な部分もあるかもしれませんよね。そのようにある種の社会実験みたいなものとしての作品作りという意味では標本を示していきたいと思っています。僕は人間性とか人間的というものが生来からあるものだと思いすぎることが人間を悩ませていると思っているので、そんなものは無いというくらいに思いたいです。自分は何かが欠けているとか何かが肥大しすぎているとか思いすぎているけど、そんなものは(生きていくうちでの)稽古でどうにでもなるという感覚はずっと持ち続けています。例えば世の中がもっと流動化したら我が子でなくても我が子のように思うことは可能だし、我が子でも我が子でないと思うことで衝突を防ぐことは可能だし、恋人にしてももう少し擬似性みたいなものを取り入れて、シミレーションして生きていると思えば良いのにと思うことがあります。基本、本物っぽいものが嫌なんですね、きっと。僕の書く戯曲は内容的にはそのようなものになると思います。
執筆に関して言うと、2022年からNHKのWDRというプロジェクト(NHKが立ち上げた脚本開発チームプロジェクト)に参加しました。それはチームで2年ぐらいかけて脚本を書くというプロジェクトで「3000万」というドラマを2024年に制作、放送しました。
最初に10人の脚本家が選ばれて、NHKでレクチャーを受け、その後連続ドラマの第一話となるものを各自が執筆しました。その中から選ばれた一つを今度は4人で共同執筆しました。チームで脚本を書くというのは初めての経験だったのですが、これがすごく面白かったんです。日本ではあまりないやり方だそうです。一人が考えた1話分の話を、みんなで8話分のエピソードに拡げて話し合った後に、各自に担当が振り分けられて脚本を書いていくというものでした。
これをやった時にチームの面白さを知りました。例えば絶体絶命の危機を乗り越えるにはどうしたら良いかといったアイディアは4人で話し合った方が絶対に豊かだし、その共同作業はとても面白いなと感じたんです。自分一人で考えられる案よりも、他の人の意見を聞いて案を練ることではるかに内容の濃いものになっていくという経験をしました。複数人で考えるこの作業はとても理に適っていると思いました。
そこで今考えているのは、チームで脚本を書くということを演劇でもやってみたいなと思っています。
今後やりたいことを教えてもらえますか。
さっくりですが、例えばイマーシブシアターのような新しい観客参加型の公演とか、演劇の作り方、公演の仕方を模索していきたいですね。
自分の戯曲をプラットフォームとして用意して、そこでチームでの脚本執筆、あるベースになっている世界観を共有した上で何人かに好きに書いてもらうといった物語の別世界、独立した世界を作ってみたいと思っています。
あとはコミュニティで演劇とは関係のない皆さんと一緒に作品を作るということも続けていきたいです。
作り手が作品を作ってそれを客席で観るだけというのではない作品づくりを、それを劇場でも、劇場でないところ、屋外とかでももっとやってもらいたいです。
演劇作品というものの捉え方を変えていけば、いろいろなことが変わっていくと思います。例えばセットを作らないとか、観客がその舞台に能動的に関わっていく形にすることで演劇的空間を作り出して経費をおさえるなどしてチケット料金を低くすることもできるのではないかと思います。その意味で、新しいかたちの演劇というものを模索していきたいと思っています。


